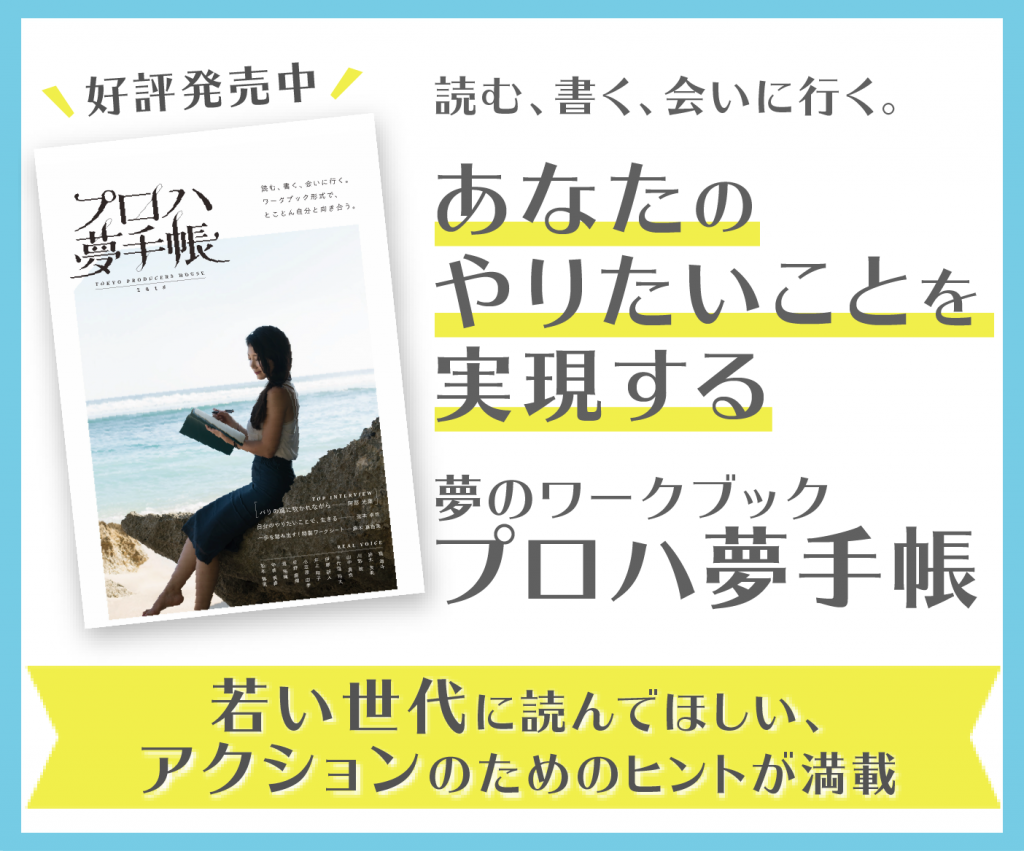もともと、プロハで冊子をつくろうとなったのは、1周年がきっかけではないのかもしれない。昨年の6月ごろだったろうか、弦本さんが「プロハで冊子を作りたい」と言い出したのがきっかけだった。当時は僕もまだプロハの運営者として、毎日メンバー集めとイベントの収益化に頭を悩ませていたころだ。
とは言っても、その頃はまだメンバーも5人程度だったし、DIYの前だったから内装もひどいものだった。プロハの魅力を伝えるというより、プロハを盛り上げるために神田錦町のいろんな飲食店を取材して記事をつくって広告料をもらってはどうか、というようなリクルートらしいアイデアだったと思う。
当時は僕も会社員で副業ができなかったし、まずは運営者としてプロハの会員を集めることに専念したいと思っていたから、冊子づくりは断ったのを憶えている。
さて、僕が会社を辞めたのは、プロハがきっかけだったと言っても過言ではない。設立者としてプロハをつくりながら、どこか中途半端だった自分がいやになり、プロハの内装ができたくらいから周囲に「夏の終わり頃に会社を辞める」と言ってまわっていた。
ただ、その頃は会社を辞めて何をするのか、どうやって生計を立てていくのかなんて決まっていなかった。貯金は内装づくりで全額はたいてしまったから、僕に残っていたのはMacBook1台と、数年の編集経験だけだった。会社の最終出社が終わったとき、決まっていたのは自分の退職報告イベントをプロハで開く予定だけ。
もちろん、仕事もゼロだった。
とはいっても、当時の僕には悲壮感なんてものはなかった。神田駅前でティッシュを配ればいい、本当にそう考えていた。ティッシュ配りを1日やれば、もらえる日給は少なくても8000円だ。毎日やれば月24万円。そう、会社員の給料とあまり変わらないのだ。当時は弦本ビルの5階の部屋があいていたから、6万円くらいで借りたらあとはどうにでもなるだろうと考えていた。覚悟というよりはこだわりがなかったのかもしれない。
人生がどうなるかなんて、辞めてみないとわからないものだ。いざ独立してみたら、編集の仕事が世の中には溢れていることが分かった。会社員だったときにはわからなかったが、編集には僕が思っていたより10倍の価値があった。単に文章を整理したり構成を考えたりするのではなく、その2歩ほど前の段階、つまり「対象の世の中における価値を再発見し、その魅力が最大限生きるようにコンテンツを引き出す」、そのための方法とアレンジが僕にできることがわかったし、世の中の多くの人、特に調子のいい中小企業がそれを求めていることがわかった。僕は比較的早くそれに気づくことができたから、編集としてウェブ制作を提案してまわった。あっという間に忙しくなった。
9月の最後の日、「独立祭」と銘打った僕の起業記念イベントには70人ほどが参加してくれ、1か月間記録していたセルフドキュメンタリーは好評を得ることができた。メンバーたちがサプライズで用意してくれた似顔絵ケーキが嬉しかった。
プロハの運営を抜けることを決めたのは、秋が終わり、冬にさしかかるころだった。僕が編集の道でプロを目指すためには、他のことを諦めなければいけない。そのためには、プロハの運営を辞めなければならない。それまで梶君と2人で決めてきたことをすべて梶君に任せて、僕はすべてを捨てる。かけてきた多くの時間とお金を手放すのは初めての経験だったし、もったいないという感覚もあった。
最後に背中を押してくれたのは、あろうことかオーナーの弦本さんだった。「任せたほうが、うまくいくこともある」、この一言で僕は決心することができた。
プロハを離れる前後は、本当にたくさんの人に迷惑をかけた。弦本さんには最後の家賃の支払いを待ってもらったし、DIYは3日ほどしか手伝えなかった。初期からいてくれたメンバーには理解されなかったし、周囲には勝手な行動に見えただろう。それまでの毎日が嘘のように、僕はプロハから遠ざかった。
そこから半年が経ち、当時の苦悩が嘘のように、プロハは盛り上がりを見せている。この冊子をつくっている途中にもどんどんメンバーが増え、メディアに登場する機会も増えた。DIYのおかげで内装は綺麗になり、女性メンバーも増えた。
冊子作りで声をかけてくれたのは、やはり弦本さんだった。「プロハの勢いをそのままに、今のこの瞬間を本にしたい」。
ウェブでもなく動画でもなく、本という形式を選んだのは、きっと僕の得意分野を考えてのことだろう。
時は2016年4月。ちょうど、自分の編集技術をもう一段階ステップアップしたいタイミングだった。しかも、印刷費はすべてオーナーが出してくれるというし、内容は僕のやりたいように任せてくれるという。半年間離れていたせいか、以前よりも客観的にプロハを見ることができたのも幸いした。昨年考えていたタウン誌のようなアイデアから離れ、メインコンセプトである「勢いを表現する」ために、メンバーのインタビューをメインに据えた。ライターをつけ、本格的に取材とDTP制作をおこなうことにした。製作期間は短く見ても1~2ヶ月。フリーランスの僕にとって決して楽な作業ではないが、他の仕事をストップしてまでやる価値があった。
4月のGW前半から取材をスタートさせ、短期間で20数名のインタビューと2つの座談会を収録した。単なる内輪の話にならぬよう、できる限り表現を一般向けにしながら、これからプロハが世の中により認知されていくために必要なことを自分なりに詰め込んだつもりだ。とても難しい作業だった。
これまで40冊近い本の制作をしてきた僕でも、これほど「誰が読むのかわからない」本をつくったのははじめてかもしれない。この本が完成して、自費出版物としてオンラインでも買えるようになったら、どんな反響があるのか、それが未知数なのだ。本が売れたら正解なのか、売れなくても何かが生まれるのか、わからない性質のものだから。
取材を続けていくと、見えてきたのはメンバー同士のつながりだった。プロハの構想当初、僕が大切にしていたのはどちらかといえば利便性やクールさだったが、それでは不十分だったと気づかされた。住み込みで管理を担当しているメンバー中心に広がる輪が、プロハを強固なつながりにしていたのだ。きっとこのつながりは単なるレンタルオフィスには生まれないだろうし、一朝一夕でつくれるものでもない。時間をかけ、金銭以外の価値を追求してこそ生まれる価値なのだ。今回の冊子でひとまず表現できたことは、プロハ1年目に生れた心のつながりの、その輪郭のようなものだろう。
タイトルを『PRODUCERS』とし、年刊形式に設定したのは、僕のアイデアだ。来年も同じタイトルで出せるとしたら、そのときは僕のねらいどおりだし、そのときはどんなメンバーがどんなことを話すのか、非常に興味がある。今回出てくれた人もきっと、次はまったく違うことを話しているだろう。変化の激しい時間を生きているプロハのメンバーたちだから、来年の今頃メンバーが総入れ替えしていてもおかしくない。それもまた「勢い」なのかもしれない。メンバーが入れ替わっても変わらず継承されるものがあるとしたら、それもまた、見てみたいなと思う。
早野 龍輝(編集者)




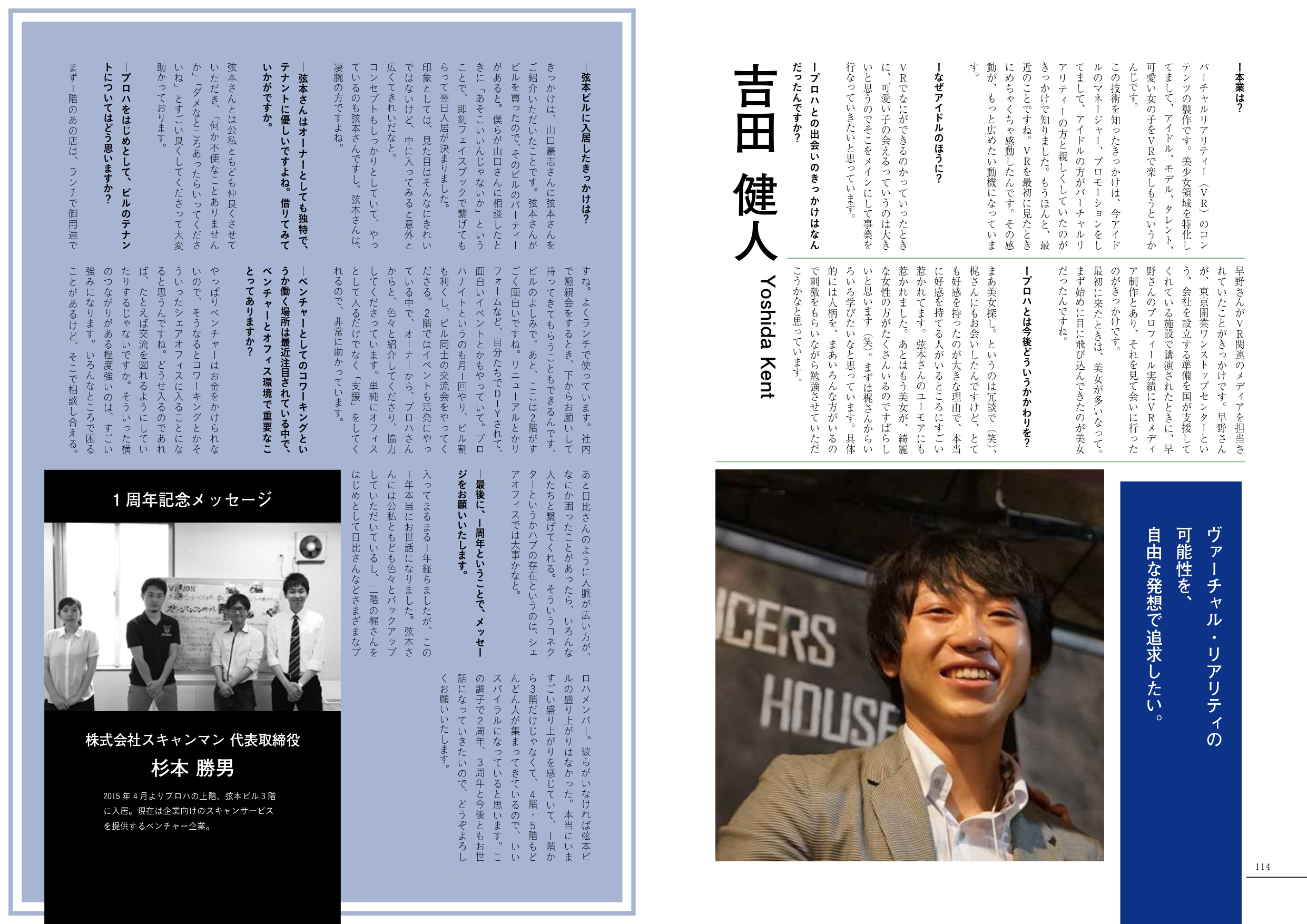









.jpg)